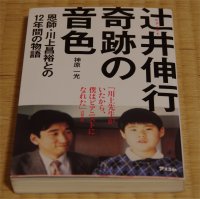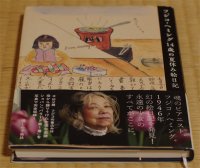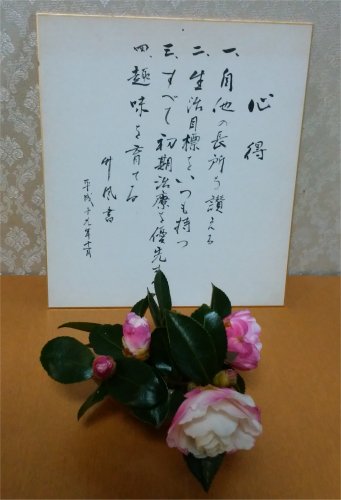6月28・29日に山梨大学合唱団OB・OG会が開催されました。コロナ明けの一昨年に4年ぶりに再開したこの会、3年連続でここ河口湖畔の合唱専門合宿施設での開催です。この日集まったのは28名で現役時代にご指導いただいた先生のご家族を交えての会となりました。
最初は先生のお嬢様:Mさんのリードで分離唱・カデンツとすすみ、歌い始めたのは讃美歌3曲。
ガリラヤのうみべ
主よこころみ
しずけきいのりの
 集まった面々、歌っている様子はこんな。こちらは女声パート。
集まった面々、歌っている様子はこんな。こちらは女声パート。

そしてこちらは男声パート。
 続いては我々としては学生時代以来初めて唱う
続いては我々としては学生時代以来初めて唱う
アルカデルトのアヴェ・マリア
約50年ぶりに歌う曲、改めてピアノを弾いてもらっての各自のパートを再確認、そしてもちろんピアノを離れて(ア・カペラ)。続いてフォーレのレクイエム、この曲は1974年に唱った曲。このOB・OG会で3回にわたっておさらいし、今回は1回通して唱ってみました。

4曲目「ピエ・イェス」はソプラノソロの曲、今回はYさんによるソロ、立派!

休憩の後は学生指揮経験者が次々と登場。時間の関係で3曲ずつで、まずはOさん指揮による
光のお宮
草原の別れ
緑の森よ
続いて幹事のKさん指揮で(写真は撮り忘れてしまった)
夏の夕べ
はるかに
われは幼く

ずっと若返ってもう一人のKさん指揮
希望のささやき
すすき
ゆけどもゆけども

最後はTさん指揮で
よしきり
背くらべ
夕焼雲
夕焼雲のソロはKさん

一日目の合唱が終わったところで先生の奥様を囲んでしばしの歓談。今年は米寿を迎えられるとのことで、誕生日には少し早いのですが
ハッピー・バースデイ
でお祝い。

この日の宿泊は15名、昨年と比べると大分少ないのですが、お陰で一人一人とゆっくりおはなしすることができました。夕食・懇親会は食べるのと話すのに夢中でついつい撮らずじまい。懇談のあとはやはり唱い始めます。で、今年は打ち合せ会であわよくば唱ってしまうという我々この会の幹事6名で讃美歌を2曲披露。
しずけきいのりの
いつくしみふかき
それから写真の通り宿泊の男性8名で男声合唱
Adoramus Te
夏の夜の※
すすき
すすめ我が同胞よ
混声合唱も唱ったのですが曲目は思い出せないな。しばらく唱った後はまたお酒を飲みながら歓談、で男性諸氏は午前1:30まで。
翌二日目も朝食の後午前中2時間やはり唱いました。この日もまずは分離唱・カデンツ、そして唱ったのは以下の曲(ちょっと記憶はあやしいが)。この部分のリードは指揮経験のない幹事である私の初体験です。
しずけきいのりの
よはふけわたりぬ
幹事:Kさん指揮で
いつくしみふかき
みたまなるきよきかみ
すすき
別のKさん指揮
ナルドのつぼ
ガリラヤのうみべ
よしきり
元学生指揮者の参加が少ないこの日引っ張り出されたのは元音楽の先生のSさん
三匹の蜂
赤い靴
青い小鳥
汽車ぽっぽ
最後は幹事でもあるKさん指揮で
洗濯ばあさん
神ともにいまして
この後昼食をとって散会となりました。
二日間よく唱いました。学生時代のようなハーモニーは望むべくもありませんが、それでも無伴奏で何十曲と楽しく唱い続けられる幸せを感じることができました。また次回も楽しく集まれることを願っています。
(123.7k)






 ピアノの調律をしていただきました、約1年ぶり。前面のボードを取り外すといつもながらのことですが鍵盤やハンマーがずらりと並んで美しい光景。調律師さんにそんな話しをすると、
ピアノの調律をしていただきました、約1年ぶり。前面のボードを取り外すといつもながらのことですが鍵盤やハンマーがずらりと並んで美しい光景。調律師さんにそんな話しをすると、 今日は我が家のピアノの調律をしてもらいました。いつもお願いしている調律師さん、いつものように手際よく作業が進んだようです。今は異常気象のためかピアノに不具合が発生することも多いのだとか、昨年は例年に無く内部でカビが発生していたピアノが多かったそうです。でも我が家のピアノはまあまあ良好な状態とのこと。指示に従って乾燥剤を数個中にいれておいたのがよいとのことでした、指示通りにしない人もいるのかな?
今日は我が家のピアノの調律をしてもらいました。いつもお願いしている調律師さん、いつものように手際よく作業が進んだようです。今は異常気象のためかピアノに不具合が発生することも多いのだとか、昨年は例年に無く内部でカビが発生していたピアノが多かったそうです。でも我が家のピアノはまあまあ良好な状態とのこと。指示に従って乾燥剤を数個中にいれておいたのがよいとのことでした、指示通りにしない人もいるのかな?