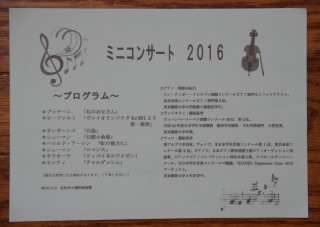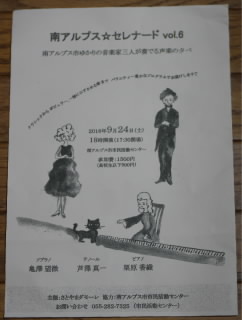第21回さらりと音楽談義 ~モチーフ:音楽への支援~
開始時間に10分ほど遅れてしまったのですが、集まりが若いためかまだ始まっていませんでした。ラッキー!これからは手作りのスウィーツも用意していただけることになったとか、前回に引き続き料理家の方の甘酒のケーキ、砂糖は使わずにさらにイチジク・レーズン・チェリーのドライフルーツも加えたオリジナルなもの、それからもう一方の手作りケーキ、イチゴと珈琲、贅沢ですね。
さて、音楽談義の始まりです。司会のKさんの歌で始まりました。
♪ ようこそ、音楽談義へ・・・・ ♪
と、会の導入から藤原先生の紹介まで歌ってしまいました。
まずは先生からおはなし、
この町(南アルプス市旧白根町)にはパイプオルガンがある。それはどうやらふるさと創生資金を活用したもののようです。「オルガンは設置したが稼働率が・・・・?」というわけで現在は市の主催でオルガン教室も行われ、その予算は年300万円にのぼるとのこと。あの時代、立派なホールがあちこちの自治体に建設されましたが、それを生かすことができるかどうかはまた別の問題。近隣のホールにうかがうと催し物が大変少なかったりで、音楽の支援というのは本当に難しい。ホールに高いピアノを購入したが、高い金で買ったから大事にしてあまり使わせないなんていうこともある。本当は弾いてもらってピアノを良好な状態に維持すべきなのだが・・・・。
更に、「企業にも音楽に支援しているところがある。」ということでそのいくつかを紹介していただきました。
・IBMでは営業と関係のないところに利益の8%を使うという社則があり、音楽・絵画・演劇など文化的なものに支援をしている。
・シャネルは銀座三丁目でコンサートを行ったり、古くはピカソやストラビンスキーを支援してきた。
・音楽家は支援がないとやっていけない、チャイコフスキーやモーツァルトもその時代その地の王の庇護の下で活動していた。
・CoCo一の社長は支援組織をつくり、若い音楽家に奨学金を提供している。
・豊橋に日本アマチュアオーケストラ連盟があるが、ここはトヨタが業績が悪いときも含めてずっと支援している。「トヨタ青少年オーケストラキャンプ」というイベントも開催されている。
このあたりから参加者も含めたトークになりました。
・司会者:Kさんのゆる体操も支援続けていただくことで育ってくるものがある。
・アメリカでは金持ちがお金の使い方をわかっている。広い土地を囲って自慢するのではなく多くの人に開放してその土地を生かす、そんな風土がある。
・我々庶民としてできる支援は入場料を払ってコンサートを聴きに行くこと。ヨーロッパなどではそういう風土があるのでは。でも入場料に見合う満足感が得られるか不安をもってしまう。
・弦楽器のコンサートで、増幅器を使っていてがっかりしたことがある。
・音楽を含めて、自然への回帰が必要。今そうしないと将来が不安。
・イタリア留学のソプラノ歌手が小さい会場で声を張り上げて歌ったことがある。音楽が楽しめなかった。場にそぐわない演奏?→会場を選ぶことも必要。
先生が以前館長をされていた音楽ホールのはなしがありました。ホール建設時の楽器購入計画は国産ピアノと大太鼓だけ。楽器の選定について行政担当者が無理解であったことなど。アメリカでは音楽学部の学部長が作曲家であると同時にマネジメントの博士号をもっといることもある。両方の知識がなければ音楽のマネジメントはできない。
参加者から、「うちの息子は音楽を聴きながら勉強をしていて、『この方が能率が上がる』というがどうでしょうか?」と大変現実的な質問。先生の回答はおおむね許容的なものでした。アメリカでは物理学学部の寮にスタンウェイのピアノが置かれている例があった。それを物理学の学生が時に弾いている。勉強のために音楽をやめるというのではなく、音楽を含めていろいろなものがその人に幅・奥行きをもたらしてくれる。
音楽療法というのがあるが、どの曲が何(の病気)に効くかというものではなく、自分が弾いたり歌ったりすることこそ音楽療法の真価が発揮されるのではないか。
等々、興味深い話が尽きず十分に伝えることは出来ないのですが、一応書いてみました。参加の皆様、はなしの趣旨・ニュアンスの違うところがありましたらご指摘をお願いします。
最後に先生が「ゆる体操」のためにとヴィオラ・ダ・モーレでみんなが唱える曲を弾いてくれました。
春の小川
花
早春賦
それから
追憶(映画音楽、私はビング・クロスビーで聴いている曲)
赤いサラファン(これは私がリクエストさせていただきました。)
最後には先生の生の演奏も聴かせていただき、嬉しい一時を過ごさせていただきました。
(14.6k)


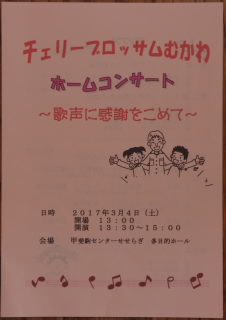



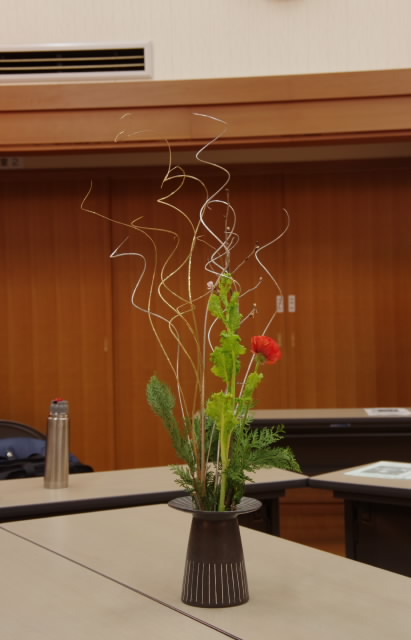

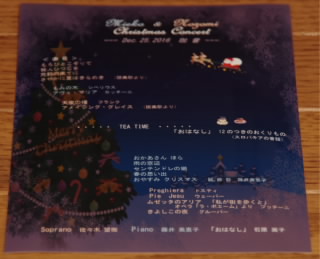

 今回は琴が登場しました、幼いときから琴を学んできた方だそうです。休憩をかねて琴の演奏を聴きました。
今回は琴が登場しました、幼いときから琴を学んできた方だそうです。休憩をかねて琴の演奏を聴きました。